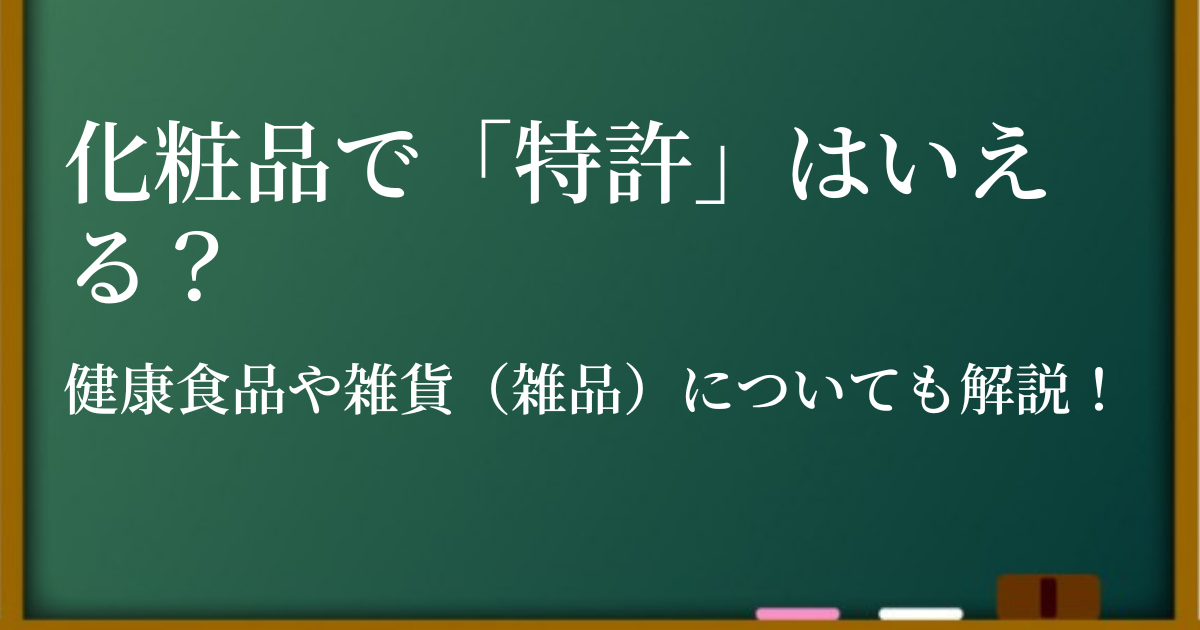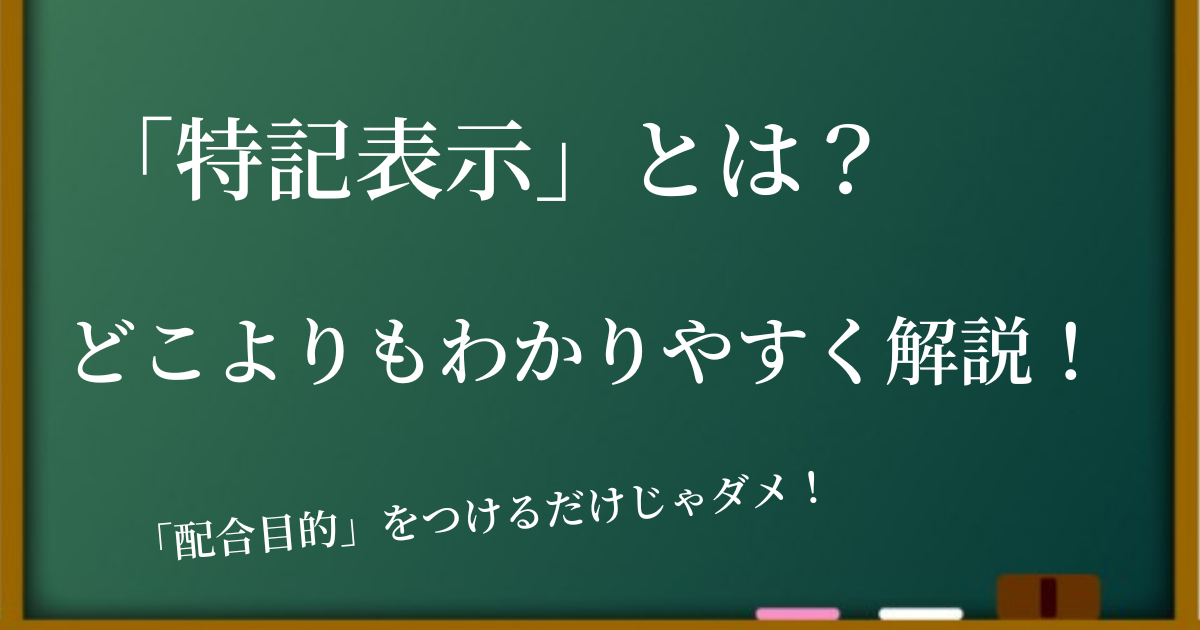YouTube広告や記事下広告などでよく見かける、外見を貶める広告、いわゆる「コンプレックス広告」。2020年には「外見上の特徴を中傷する広告、やめませんか」と題した抗議キャンペーンが炎上するなど、今物議をかもしています。コンプレックス広告は薬機法などの法律に抵触しないのでしょうか。
NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIに負けないライターになりたいけれど方法がわからない」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。
化粧品ガイドラインで規制されてはいるが…


まずは、化粧品ガイドラインのルールを見てみましょう。
F12 不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告の制限
F12.0 不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告の制限の原則
広告に接した者に、不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある表現や方法を用いた広告を行ってはならない。
(化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】)
化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】では
- 不快
- 迷惑
- 不安又は恐怖を与えるおそれのある表現
を制限しています。
現時点では違法とまではいえない
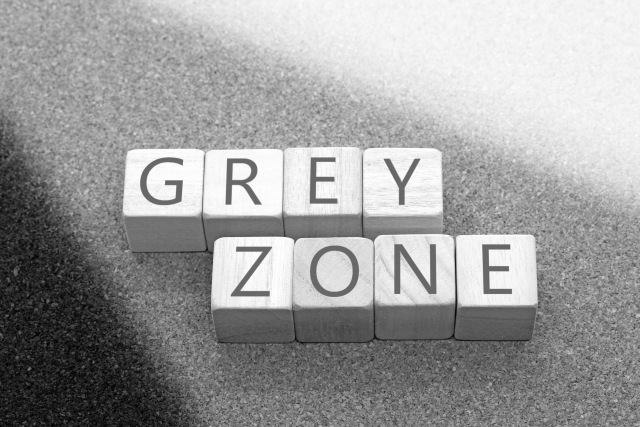
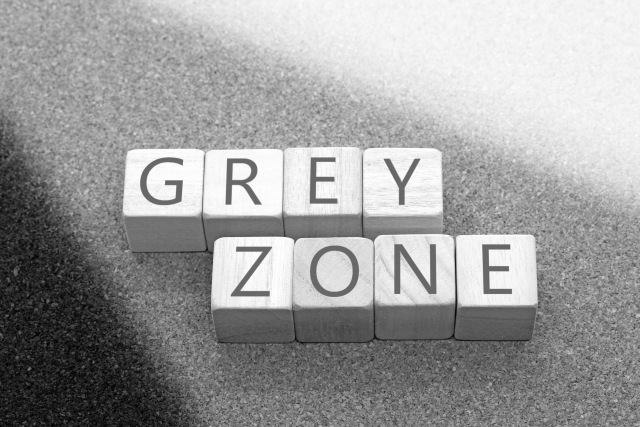
ですが、コンプレックス広告は違法とまではいえないのが現状です。
ガイドライン上でも「制限」とするにとどまっていて、明確に禁止はされていません。
F12 不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告の制限
これはヘルスケア法律が、消費者への影響が大きいものから規制するためです。
たとえば実際よりも高い効果を得られるかのように広告(誇大広告)した場合、広告を信じて購入した消費者が損害を受けます。つまり誇大広告は消費者に直接的な影響を与える行為です。
消費者への影響が大きいため、誇大広告については厳しい規制が定められているわけです(薬機法66条、健康増進法65条)。
他方コンプレックス広告は不快感こそ与えるものの、消費者に直接的な害をもたらすものではありません。そのため現時点では違法とされていないと考えられます。
ステルスマーケティングが違法でないのも、消費者に与える影響が小さいからです。
2023年10月1日からステルスマーケティングは違法になりました。


侮辱罪や名誉棄損罪も適用されません。
侮辱罪や名誉棄損罪が成立するには、誹謗中傷が特定個人に向けられていることが求められます。
ですが広告は文字通り不特定多数に向けて発信され、なおかつ誹謗中傷を目的としたものではありません。
内容が批判的・中傷的であるだけでは、侮辱罪や名誉罪は成立しないのです。
ただし各媒体の広告審査基準に抵触する


ただしコンプレックス広告は媒体の広告審査基準に抵触します。
最近では各媒体の広告審査基準も厳しくなっていて、LINEやGoogle、Yahoo!では広告ガイドラインのなかでコンプレックス広告は認めないと明記しています。
【LINE】
ユーザーが不快と感じる可能性がある表現の禁止
人体のコンプレックス部分の露骨表現や、過度な肌露出、性に関する表現が露骨なものは禁止します。また、暴力、反社会勢力を連想させる表現やグロテスクな表現等もユーザーが不快と感じる可能性があるため配信できません。(クリエイティブガイドライン|LINE広告審査ガイドライン LINE for BUsiness)
【Google】
Google では多様性を尊重し、他者への思いやりを大切にしています。そのため、衝撃的なコンテンツを表示したり、憎しみ、偏見、差別を助長したりするような広告やリンク先は許可していません。
(Google広告掲載基準第4章 掲載できない広告 |Google広告ポリシー)
【Yahoo!】
(2) 人体の局部を強調した画像を使用したもの、人体のコンプレックス部分が露骨に表現されているもの
目や口など、人体の局部を強調したものや、コンプレックス部分を露骨に表現したものは、ユーザーに不快感、嫌悪感を与える可能性があるためできません。(ガイドライン- Yahoo!広告|不適切なコンテンツ)
コンプレックス広告は違法ではない|しかしやめておくのが賢明!


コンプレックス広告は現時点では違法とまではいえません。ただヘルスケア法律の規制は時世や世論の影響を強く受け、時代とともに変わっていきます。これだけ批判が高まっていますから、今後コンプレックス広告が違法となることは十分にあり得るでしょう。逆効果になるおそれもありますし、コンプレックス広告はよしておくのが得策です。