


薬機法では「腸」に関する表現は使い方によって違反となる可能性があります。特定部位の改善や変化を示す表現は基本NGで、「腸内フローラを整える」や「腸活」などもリスクがあります。ただし「腸まで届く」など物理的な表現や、商品名を出さない形なら許容されることもあります。表現は曖昧にし、「チカラ」や「補う」といった言い換えが有効です。文脈や全体の印象にも注意が必要です。
NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIにを脅威に感じている」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。
そもそも薬機法(薬事法)って
薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。
正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正された法律です。
この法律の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることにあります
薬機法の基本ルール
薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。
【薬機法(薬事法)で禁止される表現の例】
医薬品でない商品の医薬品的効果
- 化粧水で「シワ改善」
- サプリメントで「肝機能障害が治る」
- 育毛剤で「発毛」
安全性や効果効能を保障する表現
- 絶対に安全な商品です。
- 確実に効きます。
- 副作用はありません。
「腸」はどこまでいえる?
腸の表現が薬機法違反となるかどうかは、訴求の方法やロジックによります。では、どんなケースでは違反にあたり、どんなケースでは違反にあたらないのでしょうか。
薬機法(薬事法)では特定部位の訴求は基本NG
薬機法では医薬品的な効能効果の標榜を禁止しています。医薬品的な効能効果には「身体の組織機能の一般的増強、増進を目的とする効能効果」が含まれます。
身体の「特定部位」への言及、改善や機能向上など「変化表現」は原則認められません。
【NG表現】
- 「腸の働きを改善します」
- 「腸内扇動促進」
- 「腸内細菌を活性化」
- 「健胃整腸」
- 「腸内フローラを整える」
また医薬品的か否かは、文言ではなく表示全体から判断されます。
個々の文言は問題なくとも、全体としてみたときに医薬品的な与えると不可となるおそれがあります。
たとえば、「○○(商品名)配合のオリゴ糖はビフィズス菌のエサとして働きます」といった表現は特定部位に触れていないので一見すると問題ないように思えます。しかし、文章全体から医薬品的な印象を与えるためNGとなるリスクがあります。
NG
「○○(商品名)配合のオリゴ糖はビフィズス菌のエサとして働きます」
→特定部位に触れていないが、文章全体から医薬品的な印象を与える
他方
単に成分の働き(効能効果等)を謳うことは、基本的に問題はありません。なぜなら、商品名が明示されていなければ、そもそも広告と見なされず、薬機法(薬事法)の規制を受けないからです。
OK
「(商品名を出さず)オリゴ糖はビフィズス菌のエサになります。」
→商品名がないと基本的に広告と見なされず、薬機法(薬事法)の規制を受けない


「腸」の訴求=即アウトともいいきれない
ただ、「腸」といったら必ずアウトになるわけでありません。
以前「腸まで届く」の表現が薬機法違反になるかが争われた事例があります。身体の特定部位、組織を標榜しているのでアウトとの見方もありましたが、他方で「変化」については述べていないのでセーフとの見方もあったのです。



判断が分かれるところですが、現在は「腸まで届く」は許容範囲とされる傾向にあります。
もっともこの辺りはケースバイケースで、腸まで届く表現は広告審査落ちのリスクがあります。
また腸を整える表現はトクホで許可を取得していれば標ぼう可能です。
腸内乳酸菌を増やすは「物理的効果なら可」「薬理的効果なら不可」
「腸内乳酸菌を増やす」は、ケースによります。
「サプリメントを摂取することで、物理的に、腸内乳酸菌が増える」のであれば問題はありません。
しかしサプリメントに含まれる成分が、体に作用して薬理的に腸内の乳酸菌を増やす」場合は不可となります。
- OK「物理的」「足し算的」に腸内細菌を増やす
- NG薬理的に」「体に作用して」腸内細菌を増やす
「腸」の認められる表現と認められない表現
認められない表現
- 腸の働きが改善される
- 腸が活発になる
- ○○(商品名)は××糖を配合しているので、悪玉菌を減らせます
- 腸内環境(腸内フローラ)を整える
- 腸活
- 腸の機能改善
- 整腸
- 腸内フローラに働きかけ
- 無理なく腸に働きかけます
- 腸内細菌を活性化
「改善」「活性化」といった直接的な表現だけでなく、「整える」「活発に」「働きかける」など抽象的な表現もNGリスクがあるため要注意です。
「腸が活発になる」「無理なく腸に働きかけます」については過去に摘発された事例があります。
また消費者庁は「腸活」も不可とする見解を出しています(「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に 対する要請について」)
認められる表現
次のような表現であれば認められます。
よくある質問と回答
質問:健康食品の広告で「腸活」という言葉は使えますか?
回答:健康食品の広告で「腸活」という言葉を使用することは、薬機法や健康増進法に抵触する可能性があるため注意が必要です。「腸活」という言葉自体が、身体の健康保持増進効果を暗示すると解釈されるためです。 文脈によっては、医薬品的な効能効果をうたっていると見なされ、薬機法違反となる場合があります。「毎日のスッキリをサポート」「内側から元気に」といった、健康をサポートする抽象的な表現に言い換えることが推奨されます。
質問:サプリメントの広告で「腸内環境を整える」と表現しても問題ありませんか?
回答:「腸内環境を整える」という表現は、身体の特定の部位への作用や機能の改善を示唆するため、医薬品的な効能効果とみなされます。そのため、医薬品や特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品として許可や届出がされていない一般的な健康食品の広告で使用することは薬機法違反にあたります。 代わりに「内側からキレイに」「毎日のリズムを応援」といった、身体の変化を直接的に表現しない言葉を選ぶ必要があります。
質問:「便通を改善する」という効果をサプリメントの広告でうたうことはできますか?
回答:「便通を改善する」という表現は、病気の治療や身体機能の増強を目的とする効能効果にあたるため、医薬品や特定保健用食品(トクホ)などを除き、一般的な健康食品の広告で使用することは薬機法で禁止されています。これは「お通じが良くなる」といった表現も同様です。消費者に誤解を与えないよう、「毎日のスッキリを応援」「気分爽快」などの表現を用いることが適切です。
質問:「腸まで届く」という表現はサプリメントの広告で使っても良いですか?
回答:「腸まで届く」という表現は、サプリメントが胃で溶けずに腸まで到達するという製品の物理的な特性を示すものであれば、直ちに薬機法違反とはなりません。しかし、その表現が「腸に作用する」「腸の働きを良くする」といった医薬品的な効果を暗示する文脈で使われると、薬機法に抵触するリスクが高まります。 表現の仕方には注意が必要です。
「腸」は注意が必要なワード|必ずしも不可ではないが…
薬機法では「腸」は必ずしもNGとはなりません。「腸」に関する表現は使い方によって認められる場合と認められない場合があります。特定部位の改善や変化を示す表現は基本NGで、「腸内フローラを整える」や「腸活」などもリスクがあります。
Life-lighterでは、日本でただ一人消費者庁の公的文書の誤りを指摘・是正に貢献した実績をもち、消費者庁と公正取引協議会の資格「景品表示法務検定」のアドバンスクラスを取得済(合格者番号APR22000 32)、わかさ生活に薬機法の専門家としてインタビューをうけた実績などをもつ専業薬機法ライターが広告法務をサポートしています。
- 薬機法ライティング
- 広告制作
- 薬機法チェック(非弁行為に当たらない方法)
- セミナー
- 社内研修
などのサービスを提供しているほか、視聴期限なしで永久伴走サポート付き、薬機法チェックやリライトのノウハウもお伝えしている「A×薬機法ライター養成講座」も運営しています。(現在モニター価格で募集中)まずはお気軽にご相談ください。




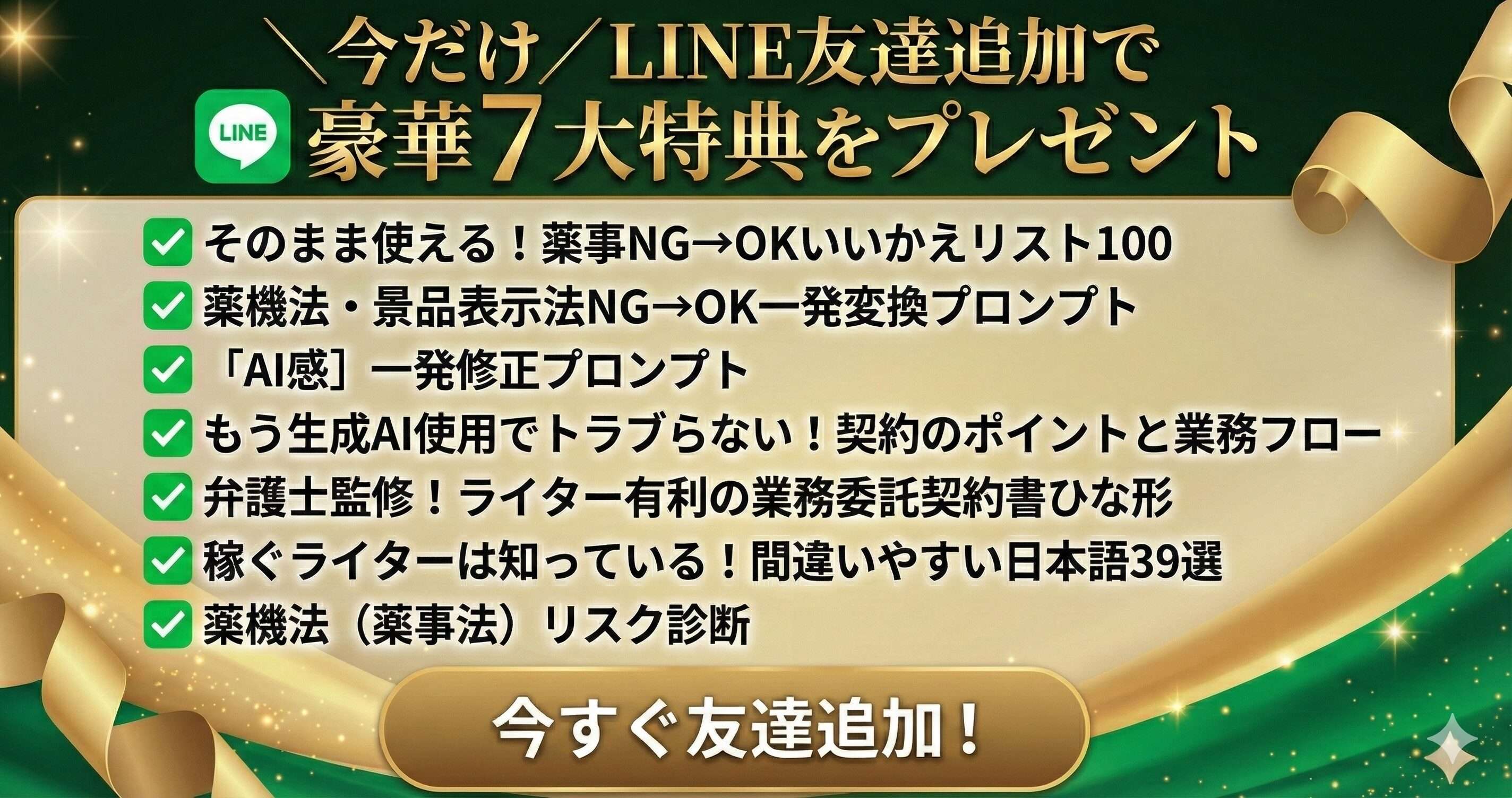
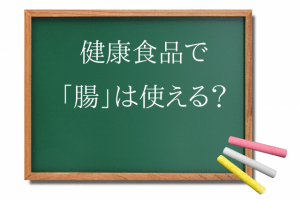







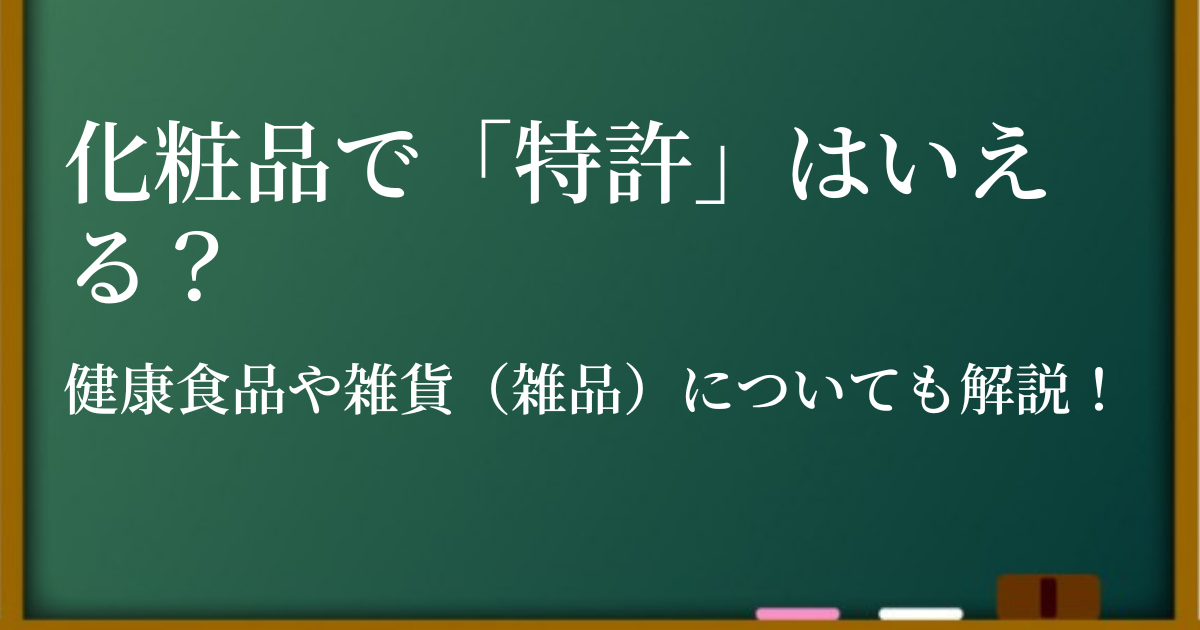
コメント