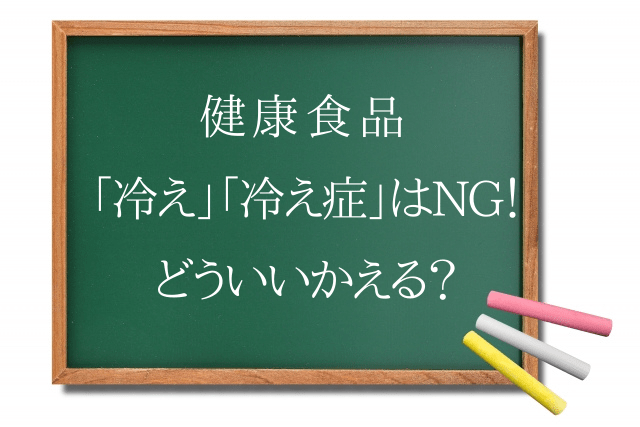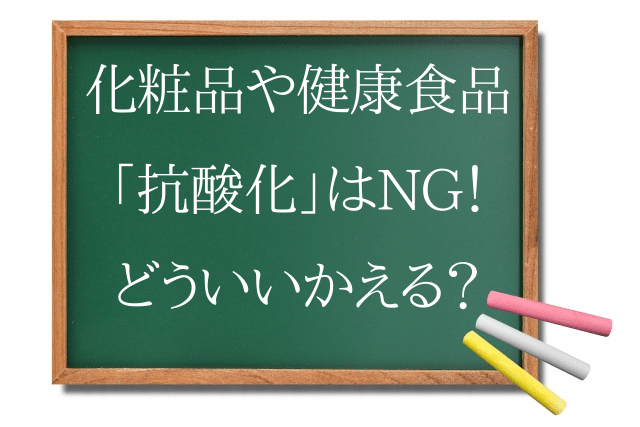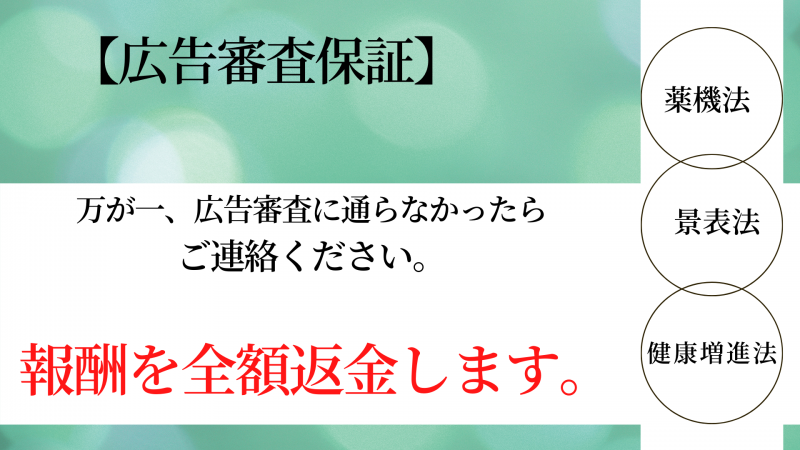- ステルスマーケティング規制に触れず、商品を売りたい…
- 薬機法だけでは意味ないんだよ
- 広告関係の法則を網羅してるライター、いないかな…
- イメージを損ねずに売上を伸ばしたい…
こんなお悩みありませんか。弊社ならすべて解決できます。
消費者庁の誤りを改善させた専門性×豊富な実績×好かれて売れる訴求=イメージUPと利益拡大の両立
<提供サービス>
◆記事制作
◆広告やウェブサイトのリーガルチェック
◆LIVEコマースの薬事カンニングペーパー制作
◆ライター養成講座
◆YouTubeなど動画コンテンツのスクリプト制作
◆法務コンサル
◆広告表現に関するご相談
◆アフィリエイターへの法律指導
※TV出演実績あり
提供サービス
薬機法や景品表示法、といった法律の遵守はもちろん、好かれて売れる表現でブランディングと利益拡大を両立。
徹底したエビデンスリサーチで、誤りのない高品質な記事をご提供。貴社のサービスによって書き分けます。
成果物の一例はこちらからご確認いただけます。
弊社一番人気のサービスです。
「法の遵守」「訴求力」「消費者感情への配慮」
令和の美容健康広告で売るための3大要素を兼ね備えた、好かれて売れるホワイトな代替表現をご提案。薬機法だけでなく、景品表示法や健康増進法、特商法あはき法など関連法規や公正競争規約も網羅しており、盤石の体制でご出稿いただけます。
※広告審査保証キャンペーン実施中
視聴者の興味を惹きつけるスクリプトをご提供。法律だけじゃなく、公正競争規約、各媒体の審査にも精通している弊社だからこそ、安心してご出稿いただけます。
豊富な実績と確かな知見で、攻めと守りの両面から好かれて売れる広告法務をサポート。貴社の方針に合った戦略を打ち出します。
アフィリエイターにもわかりやすく、かつ実践的なマニュアルをご提供。貴社の足を引っ張っていたアフィリエイターが一転、戦力に変わります。
貴社の商品・サービス「法的に訴求可能なライン」や「気をつけるべき表現」「表現方法」などをまとめた資料をご提供。
リアルタイムで商品を販売するLIVEコマースでは、「どこまで言っていいんだっけ」となってしまうもの。カンニングペーパーを見ながら進めることで慌てずに対応でき売上UPにつながります。
コンプレックスを刺激するのではなく、心情に配慮した訴求・クリエイティブでストーリーを紡ぎます。ユーザーの心をとらえ、コンバージョンはもちろん、リピートやファン化促進、ロイヤルカスタマー化も狙えます。
大手企業や編プロで発注者指導をしている講師が、実務で活きるカリキュラムで薬機スキルを伝授します。AIが進化するほど稼げるライターになりませんか?
Life-lighterでは、違反しないだけじゃない、好かれて売れる上質なコンテンツをご提供しております。
- 下品な広告は打ちたくない
- 品性を重んじる
- ブランディングしつつ、売り上げを伸ばしたい
といった企業様のおちからになることができます。
【広告審査保証キャンペーン実施中!】


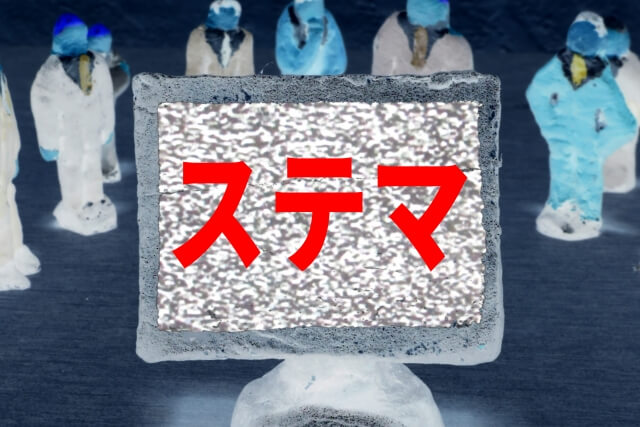

-「便秘」は使える?-2.png)
-「便秘」は使える?-12.png)